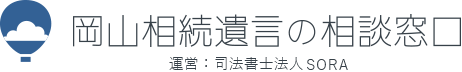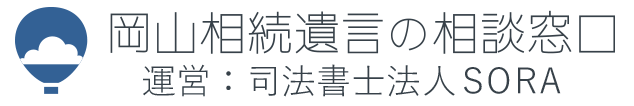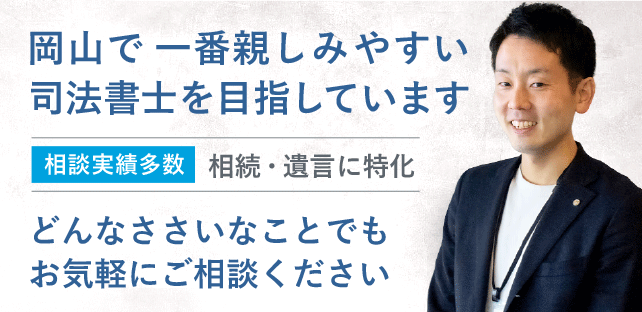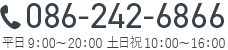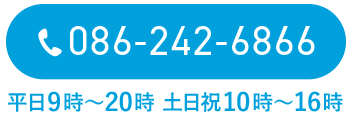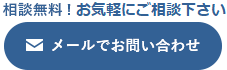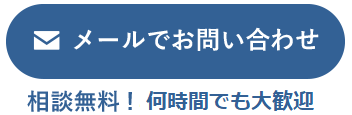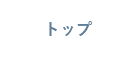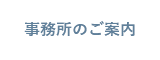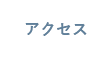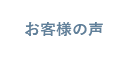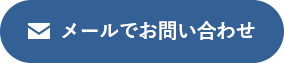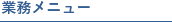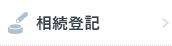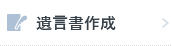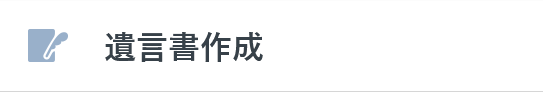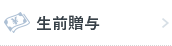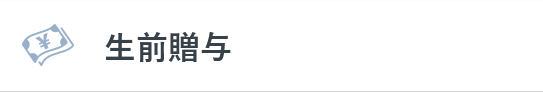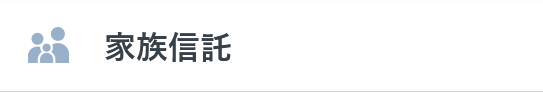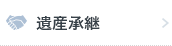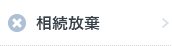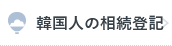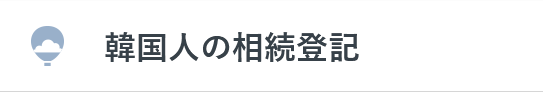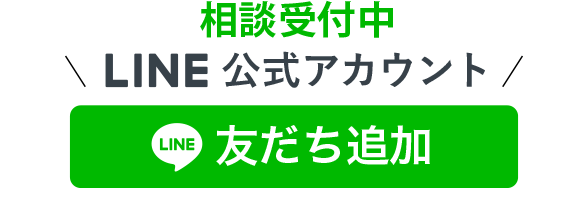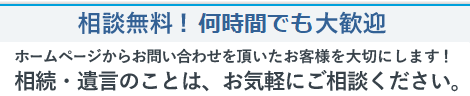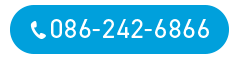相続放棄
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、
それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても
自動的に引き継ぐことを言います。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や連帯保証人になっていた場合、
金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。
自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、
大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、
これは間違った認識ですので、ご注意下さい。
相続放棄が必要なケース
相続放棄が必要な典型的なケースは、プラスの財産よりも、借金や滞納している税金などのマイナスの財産が多い場合です。
この場合、相続放棄をしなければ、借金の負担を引き継いでしまいます。
特に、生命保険金(死亡保険金)の受取人となっている場合には、相続放棄しても生命保険金は受け取れますので、
相続放棄した方がよいでしょう。
なお、同順位の相続人全員が相続放棄すれば、次順位の相続人に相続資格が移り、
当初は相続人でなかったのに相続人となることがあります。
この場合にも、自らが相続人となったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなければ、借金を引き継いでしまいます。
他の親族とかかわりたくない場合にも、相続放棄した方がよいことがあります。
たとえば、兄弟姉妹・おじ・おばの相続人になることがありますが、大人になってからは交流がないケースもよくあります。
相続放棄すれば、このような親族とかかわりを持たずにすみます。
3ヶ月後の相続放棄
相続放棄や限定承認の判断は、相続発生を知ってから3ヵ月以内にしなければなりません。
この短期間で、被相続人の財産や借金をしっかり調査しなければなりません。
しかし、実際全ての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することはなかなか難しいことです。
このようなときは、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。
それには、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。
ですから、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、
この延長の請求をおすすめします。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、
すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難ですから、このような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。